「光が死んだ夏」の読者にとって、舞台は三重県のどこなのか、モデル地を聖地巡礼したい方も多いと思います。
そこで今回は、舞台となったモデル地に焦点をあてて、
- 舞台はどこ?
- 三重県のモデル地は?
について詳しくまとめました!
聖地巡礼したい方は、舞台のモデルとなった場所の地図や住所も載せているので必見です。
また、三重県特有の方言の意味も調べてあるので、ぜひ最後までご覧ください。
光が死んだ夏の舞台はどこか、三重県モデル地についても知りたい方におすすめの記事となっています。
もくじ
光が死んだ夏の舞台はどこ?
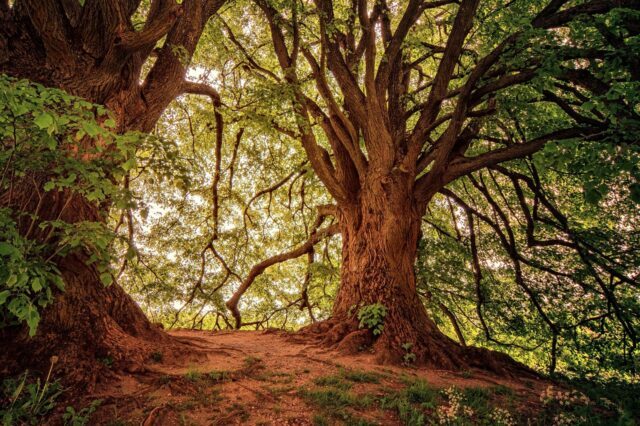
光が死んだ夏に出てくる、山間の村「クビタチ村」は、一体どこが舞台となっているのでしょうか?
特定の地名を明かしていないものの、作者が「東海地方の山間部の空気感を意識した」と語っているので、三重県津市・度会町・大台町・熊野市・名張市・鈴鹿市などがファンの間で聖地となっています。
物語の舞台は、三重県南部から奈良県にかけての山間部集落と考えられています。
作品内には現実の三重県南部〜奈良県との地理的・文化的接点が多数散りばめられています。
光が死んだ夏は奈良県も舞台?
メインの舞台は三重県とされていますが、奈良県御杖村(みつえむら)の風景も複数モデルとなっています。
| シーン・描写 | モデル地 |
|---|---|
| 神社の鳥居・階段があるシーン | 御杖神社の鳥居・苔むした階段と一致 |
| 不気味な祠や地蔵が登場するシーン | 「首切地蔵」および道標が建つ実在の場所がモデルと推測 |
御杖神社
〒633-1301 奈良県宇陀郡御杖村神末1020
首切地蔵と道標(願主行悦)
〒633-1301 奈良県宇陀郡御杖村神末
御杖村の風景は、日常というよりも作品の「異常」な空気感を視覚的に強める重要な舞台となっています。
光が死んだ夏の三重県モデル地を聖地巡礼!

作者のモクモクれんさんは、三重県に取材に行きたいと考えていたようですが、コロナ禍で下見に行けなかったようです。
ここでは三重県のモデル地となったスポットを聖地巡礼できるよう、マップと住所を併せてまとめました。
光が死んだ夏の三重県モデル地①学校
よしき達が通う高校、希望ヶ山高校の校舎は、三重県立白山高等学校(津市白山町)がモデルになっています。
エンディングの取材協力にも、「三重県立白山高等学校」と名前があり、作品内の校門とも一致します。
三重県立白山高等学校
〒515-3133 三重県津市白山町南家城678
光が死んだ夏の三重県モデル地②スーパー
第2話で、よしきが暮林さんに声をかけられるシーンにはスーパーの外観が背景に映っています。
そこは、イオン久居店(津市久居明神町) がモデルと言われています。
イオン久居店
〒514-1101 三重県津市久居明神町風早2660
光が死んだ夏の三重県モデル地③駅
よしきと光が降りた駅は、尾鷲市にある三木里駅が舞台となっています。
三木里駅は、JR紀勢本線のローカルな無人駅で平屋の素朴な駅舎が、エンディング映像に登場しています。
三木里駅
〒519-3811 三重県尾鷲市三木里町
光が死んだ夏の三重県モデル地④給水塔
光が死んだ夏では、作中に蒸気機関車用のレトロな給水塔が描かれています。
特徴的な形の給水塔は、三重県津市美杉町奥津に実在する、レトロな給水塔をモデルとしていると思われます。
旧国鉄名松線伊勢奥津駅給水塔(登録文化財)
〒515-3531 三重県津市美杉町奥津1216
光が死んだ夏の三重県モデル地⑤家
よしきと光のシーンには、家も頻繁に描かれています。
そのモデルは作者の祖母の家をイメージしたものです。
古いスリガラスや黒電話、勝手に出入りする近所の人など、両親と帰省した際に見た風景が本作にも使われています。
「山と海との境目のような立地の狭い集落で、家がみっちりと密集していた」場所のイメージが、幼い頃に訪れた祖母の家だったのでしょう。
残念ながら、モクモクれんさんの祖母の家の都道府県については分かりませんでした。
家のモデルは三重県ではない可能性もあります。
光が死んだ夏の方言は三重弁?
光が死んだ夏の舞台は、三重県南部から奈良県にかけての山間部集落がモデルであることが分かりました。
風景描写だけでなく、方言からも独特の地域性を漂わせています。
関西弁のような、でも聞きなれない語尾がどこの方言なのか気になりますよね。
「登場人物に特徴的な方言を使わせたかった」とし、関西弁とは違う「東海地方の山間部、特に三重県南部(東紀州地域)」を参考にしたようです。
| 方言 | 意味 | 使用シーン |
|---|---|---|
| ケッタ | 自転車 | 少年たちが移動手段として使う場面など |
| ツル/机つって | (机を)運ぶ | 教室や部屋の片付け、移動を指示する日常会 |
| ごおわく | 怒り・腹が立つ | 登場人物が不快な感情を露わにするシーン |
| せやに | そうだよ(同意) | 会話の相槌や肯定の返答 |
| あかんに | だめだよ | 注意・禁止のニュアンスを含むセリフ |
| 思い出されやんな | 思い出せないな | 過去や記憶を振り返る場面でのぼんやりとした感情表現 |
| おいないさ | いらっしゃい | 商店や人の出迎えの場面など |
| ずっこい | ずるい | 子供っぽい非難や嫉妬など表現に |
| 入り浸ったろけ? | 入り浸っちゃおうか | 誘い・提案のシーンなどで使われるフランクな言い回し |
意味が分からず、なんとなくで読んでいた方も多いのではないでしょうか?
方言の意味が分かって、もう一度読み返してみると、物語の理解が深まって、面白さが倍増すると思います。
光が死んだ夏の方言は岐阜弁?
作品の舞台も三重県で、方言も三重弁のものが多いですが、SNSでは岐阜の方言に似た表現も含まれていると話題です。
いくつかの方言は、岐阜弁にも共通して使われるものがあります。
| 方言表現 | 意味 | 岐阜弁との共通性 |
|---|---|---|
| ずっこい | ずるい | 岐阜でも「ずるい」の意味で使う。中部~関西圏全般で広く使用される言い回し。 |
| 〜しとる/〜しとった | ~している/していた | 岐阜でも同じ形で使用される。中部・関西共通の進行形表現。 |
| おいないさ | いらっしゃい | 岐阜の一部(特に郡上・飛騨地方)でも使われることがある。 |
| 〜やに | 〜だよね/〜だよ | 「やに」は岐阜弁でも使用され、「せやに(そうだよね)」などは共通表現。 |
| あかんに | ダメだよ | 「あかん」自体は関西弁ですが、岐阜南部でも広く使われる |
「光が死んだ夏」は、特定の方言ではなく、複数地域の言葉をベースに、雰囲気で組み立てています。
作品に出てくる方言は岐阜でも使用されるものもありますが、純粋な岐阜弁ではないということです。
どこか田舎の方言のような、でも特定できない曖昧さが、「恐怖」や「違和感」を助長させるスパイスになっていると感じます。
光が死んだ夏の舞台はどこ?三重県のモデル地を聖地巡礼!まとめ

ここまで、「光が死んだ夏の舞台はどこ?三重県のモデル地を聖地巡礼!」について紹介してきました。
大まかに三重県を舞台として、様々な場所をモデルにして組み合わさった作品となっています。
特に学校、スーパー、駅、給水塔などの背景は、リアルな建物や風景をモチーフにしており、読者に没入感を与えてくれます。
実在しない場所も描くことで、違和感やミステリアスさを助長しているのではないでしょうか。
独特な方言は関西弁ではなく、三重県や岐阜県といった東海地方で使われる言葉が出てきています。
作者が描く風景は、田舎の懐かしさの中に恐怖心を上手に組み込んいる不気味さが怪談のようです。
聖地巡礼したい方にとって、「光が死んだ夏の舞台はどこ?三重県のモデル地を聖地巡礼!」が参考になれば嬉しいです。
